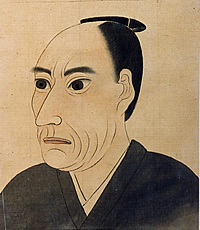| 江川英龍(坦庵)年表 |
1801年
(享和元) |
父英毅(ひでたけ)、母久子の次男として韮山で誕生 |
1818年
(文政元)
|
江戸に出て、神田の神道無念流、岡田十松道場に入門
本格的な剣道を修業する。

剣道に励む 版画 森英二郎
兄弟子 斎藤弥九郎につく。二年後には免許皆伝となった。 |
1821年
(文政四) |
兄 英虎が病死したため嫡子となる |
1823年
|
旗本北条氏征(うじまさ)の娘と婚姻 |
1824年
|
韮山代官職見習(江戸、本所屋敷) |

母久子を見舞う
版画 森英二郎
|
1830年
(天保元)
|
母久子 病死
母久子からは、「早まる気持をおさえ、冷静な気持を常に持つように」と「忍」をさとされ、以後「忍」の文字を書き、懐中に携帯した。 |
| 1834年 |
父英毅 病死 |
1835年
|
韮山代官就任
江戸にて、高野長英、渡邊崋山等の
蘭学者の集い「尚歯(しょうし)会」が始められる。
後に「尚歯会」に参画。 |
1837年
|
剣友 斉藤弥九郎を手代に、大塩平八郎の乱後弥九郎と甲州微行(びこう)に出、一揆(いっき)を事前に抑える。
このように領内における英龍の
善政に対し、民衆から
「世直し大明神」といわれた。 |
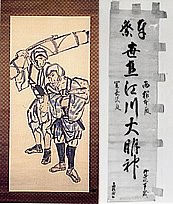
甲州微行(坦庵作) |
1838年
|
米船モリソン号が浦賀に来航以来、英龍や川路聖謨(としあきら)
等は、海外文明の進歩度合や非戦論を幕府に差し出す。 |
1839年
|
鎖国維持派目付 鳥居耀蔵(ようぞう)の副官として、浦賀付近を測量。 |

測量の道具 |
1841年
|
高島秋帆(しゅうはん)、江戸 徳丸原(とくまるがはら)で砲術の実演をする。その後入門し、高島流砲術を修める。 |
1842年
|
江川塾を開き、佐久間象山をはじめ、全国の多くの藩より韮山へ入門者が訪れた。
一方、韮山で大砲(青銅製)、
小銃製造が本格化。 |

反射炉敷地内 モルチール砲 |
1846年
(弘化三) |
蘭、英、仏、露等、外国船の来航しきり。
開国を求められる。幕府の主要ポストも移動しきり。 |
1848年
(嘉永元) |
砲製造先進の佐賀藩主 鍋島直正と会(かい)す。後々、反射炉や洋式鋳砲の技術交流がなされた。 |
1849年
|
英艦マリナー号 幕命を受け下田より退去させる。
(蜀江(しょくこう)の錦)
| イギリス軍艦マリナー号が下田へ入港し、英龍が時の下田奉行にかわって退去交渉をした折、この装束を着、立派な統率者として、軍艦を退去させることに成功した。 |
|

蜀江の錦の袴 |
1850年
|
実子に種痘をし、成功。種痘接種を広める。 |
1851年
|
農兵の必要性を上申。 |
1853年
|
米国使節ペリー浦賀入国。
幕府海防掛(かかり)勘定吟味役格となる。
品川台場築造の命を受け、設計、起工。
高島秋帆を手代にし、中浜(ジョン)
万次郎を手附にする。
反射炉築造の命を受ける。 |

ペリー |
|
1854年
(安政元)
|
ペリー再来日。日米和親条約調印。
下田、函館開港される。
中浜万次郎は徳川斉昭(なりあき)の
反対で通訳方としては使えず、
蘭英辞典の作成を命ず。
反射炉を韮山鳴滝に築工始める。
品川台場完成。 |

江戸時代の洋書 |
ディアナ号座礁見分救助、新造船
建造を戸田にて着工。
病勢悪化、幕府より勘定奉行の
命下り江戸へ。 |

ヘダ号模型
(戸田村造船郷土史料博物館蔵) |
1855年
|
1月16日本所にて死亡。
韮山本立寺に葬られる
子英敏(ひでとし)が代官を
受けたのが16歳。 |

英龍墓 |
1856年
|
実質的には柏木総蔵を中心に鉄砲方 芝新銭座大小砲習練場を初め台場御用、及び大砲鋳造等が引きつがれた。
この習練場には諸藩士の入門がつづき、黒田清隆、大山巖等
多くの人材を輩出した。 |
1858年
|
反射炉による鉄製砲完成 |
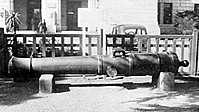
靖国神社のカノン砲(韮山製) |
|
1862年
|
英敏死亡。
弟英武(38代)相続最後の代官と
なった。 |

第38代英武 |