|
|
| 江川家の沿革(歴史) |
|
|
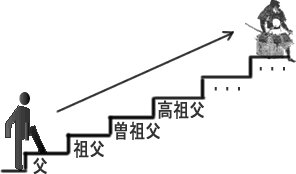 私たちは自分の先祖の代々を、どのくらいまで遡ることができるでしょう。 私たちは自分の先祖の代々を、どのくらいまで遡ることができるでしょう。
|
| 初代〜8代 |
初代は大和源氏の祖とされる源頼親(みなもとのよりちか)。その祖父は清和天皇の皇孫で臣籍降下した源経基(つねもと)ということで、江川家は、清和源氏のうちの大和源氏の流れです。
初代が大和守(やまとのかみ)となって、大和国(奈良県)に勢力を築き以後宇野を姓として8代までは大和国に居りました。 ちなみに、後世、自家の歴史を詳しく取り調べまとめあげた人に35代江川英毅(ひでたけ)と、その孫の英武(ひでたけ)がいます。各々「大和将軍三十五世孫」「大和将軍三十八世孫」と刻した印を持ちました。自家の歴史の重みを充分かみしめたというあじわいの深さがあります。 英武の孫である41代現当主も、近年専門家二十余名による江川文庫調査団をたちあげ、英毅・英武よりもっと大規模な整理・研究が開始されました。さてさて「大和将軍四十一世孫」の印は生まれるでしょうか。 |
| 28代〜38代 |
私たちの知っている“代官の家”というのは江戸時代の江川家のありようです。28代の江川英長(ひでなが)が、徳川家康に仕えて代官になり、以後明治に至るまで、代々“お代官さま”になりました。この時代、家督相続した当主は皆太郎左衛門を称しましたので、代官役所の公文書の署名もこれ。注意しないと、どの太郎左衛門さんかまちがえそうです。
家譜では、英長以後の代々のことは、かなり詳しく記されていて、事績がわかります。とりわけ傑出した人物として36代江川英龍(ひでたつ)がいますが、これは項を別にして詳しくお伝えします。 |
| 9代〜22代 |
平安時代に戻りましょう。
9代宇野親信(うのちかのぶ)が、従者と共に伊豆のヤマキと呼ばれた現在地に移住しました。時は平安時代の最末期。それで、近くにいた源頼朝の伊豆旗揚げに参加したと家譜は伝えています。以後、鎌倉幕府・室町幕府に仕えて、ヤマキの豪族として勢力をもったようですが、詳しいことはあまりわかっていません。 ひとつ特筆することは、16代英親(ひでちか)が日蓮に出会って改宗し、それ以後今日に至るまで熱心な日蓮宗の家になったことです。 いったいに、中世の江川家については、不明なことが多いのです。江川姓への改姓も21代英信(ひでのぶ)のあたりらしいのですが、それ以前にも人が江川殿と呼んだようですし、なぜ江川という名になったのかも、説が分かれています。つかさどった荘園の名からだという説と、近くを流れていた川の名からだという説などです。 |
| 23代〜27代 |
しかし、少なくとも、北条早雲が伊豆討入(うちい)りをして韮山城に入った時に、23代英住(ひでずみ)が早雲の家来となり、以後、後北条氏に仕えたこと、また江川酒を醸造して名声を得ていたことは、江川家以外の史料があって確かめられます。後北条氏に仕えた約100年のことを、家譜はある程度伝えていますが、これまで、それらが本当なのか確かめる史料を見い出せませんでした。けれども、先程お伝えした江川文庫調査団によって江川家の中世が明らかになりつつあります。いずれ、それらが発表されることになるでしょうから、楽しみにお待ち下さい。 |
| 江川家の沿革トップへ | 次 へ |